2011年08月03日
伊勢遺跡と邪馬台国その2
伊勢遺跡を語る前にまず
銅鐸のお話をしなければなりません。
ちょっと我慢して読んで下さいね。
明治14年(1881)野洲町大岩山に遊びに来ていた14歳と16歳の少年が
銅鐸を見つけました。この時発見された銅鐸の数14個。その後時代を
経て昭和 37年、小篠原地先(こしのはらちさき)の東海道新幹線の土
取工事現場から、計10個の銅鐸が発見されます。これで合計24個の銅
鐸が出たことになります。この銅鐸は野洲市の「野洲町立歴史民俗資
料館」に展示されています。


あまりにも銅鐸が多く展示されていることから「銅鐸博物館」とも
呼ばれる。
日本一の大きさを誇る銅鐸もここで発見されました。

日本一最長の銅鐸、なんと134.7㎝
この大岩山で発見された銅鐸にはひとつの特徴がみられます。
近畿地方以西で造られた近畿式銅鐸
と
東海地方で造られた三遠(さんえん)式銅鐸
がここで同時に発見されています。
近畿式銅鐸

上部に渦巻き状の飾りがついています。
三遠(さんえん)式銅鐸

飾りがついていません。

当時、銅鐸は日本の各地にあった小国のシンボルで
あったといいます。
各地域で特徴を持っていた様々な銅鐸が
ここ、大岩山で同時に見つかっています。
同時に・・・・
同時に発見される例は日本中のどこをみても
ここだけだといいます。
どういう意味があるのでしょう?
2~3世紀、日本国内では小国間どうしでの
争いが絶えませんでした。
ある時、争っていた国々がここに一同に集まり
自国のシンボルである銅鐸を埋め、
何らかの儀式が行われた。

弥生時代、銅鐸が埋められた時の想像図(野洲銅鐸博物館)
つまり国々の争いが収まり、連合国家を造る動きが
ここであったのではないかという推測がつきます。
日本建国神話を記した「古事記」や「日本書紀」でよく出てくる
八百万神(やおよろずのかみ)
八百万神が当時の日本各地の首長だったのでは?
という、想像も膨らみます。
この八百万の神が一同に会した場所は
そう、天安河(あまのやすかわ)
あまのやすかわ・・・
やすかわ・・
野洲川!
当時、野洲あたりを支配していた豪族は
安(やす)氏
う~~ん、
いろいろなキーワードが一致してきますね。
(無理やりだ!っという意見も受け入れます)
そして、ここから10キロほど離れた
野洲川のほとりに
伊勢遺跡があります。
そう、
30棟の建物を円形に配した伊勢遺跡。
詳しくはこちらへ
「伊勢遺跡と邪馬台国」
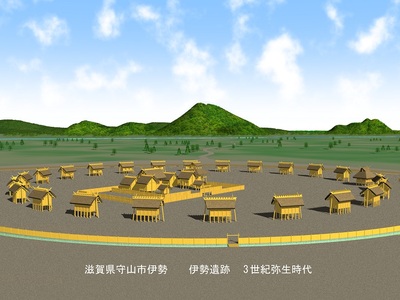
何ら関係があってもおかしくはありません。
今度こそ、その30棟の謎に迫ります。
銅鐸のお話をしなければなりません。
ちょっと我慢して読んで下さいね。
明治14年(1881)野洲町大岩山に遊びに来ていた14歳と16歳の少年が
銅鐸を見つけました。この時発見された銅鐸の数14個。その後時代を
経て昭和 37年、小篠原地先(こしのはらちさき)の東海道新幹線の土
取工事現場から、計10個の銅鐸が発見されます。これで合計24個の銅
鐸が出たことになります。この銅鐸は野洲市の「野洲町立歴史民俗資
料館」に展示されています。


あまりにも銅鐸が多く展示されていることから「銅鐸博物館」とも
呼ばれる。
日本一の大きさを誇る銅鐸もここで発見されました。

日本一最長の銅鐸、なんと134.7㎝
この大岩山で発見された銅鐸にはひとつの特徴がみられます。
近畿地方以西で造られた近畿式銅鐸
と
東海地方で造られた三遠(さんえん)式銅鐸
がここで同時に発見されています。
近畿式銅鐸

上部に渦巻き状の飾りがついています。
三遠(さんえん)式銅鐸

飾りがついていません。

当時、銅鐸は日本の各地にあった小国のシンボルで
あったといいます。
各地域で特徴を持っていた様々な銅鐸が
ここ、大岩山で同時に見つかっています。
同時に・・・・
同時に発見される例は日本中のどこをみても
ここだけだといいます。
どういう意味があるのでしょう?
2~3世紀、日本国内では小国間どうしでの
争いが絶えませんでした。
ある時、争っていた国々がここに一同に集まり
自国のシンボルである銅鐸を埋め、
何らかの儀式が行われた。

弥生時代、銅鐸が埋められた時の想像図(野洲銅鐸博物館)
つまり国々の争いが収まり、連合国家を造る動きが
ここであったのではないかという推測がつきます。
日本建国神話を記した「古事記」や「日本書紀」でよく出てくる
八百万神(やおよろずのかみ)
八百万神が当時の日本各地の首長だったのでは?
という、想像も膨らみます。
この八百万の神が一同に会した場所は
そう、天安河(あまのやすかわ)
あまのやすかわ・・・
やすかわ・・
野洲川!
当時、野洲あたりを支配していた豪族は
安(やす)氏
う~~ん、
いろいろなキーワードが一致してきますね。
(無理やりだ!っという意見も受け入れます)
そして、ここから10キロほど離れた
野洲川のほとりに
伊勢遺跡があります。
そう、
30棟の建物を円形に配した伊勢遺跡。
詳しくはこちらへ
「伊勢遺跡と邪馬台国」
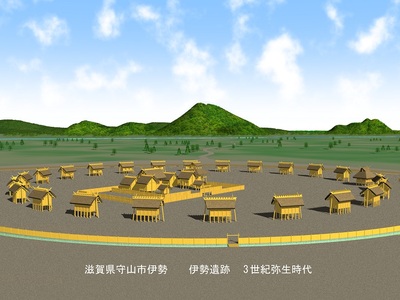
何ら関係があってもおかしくはありません。
今度こそ、その30棟の謎に迫ります。


